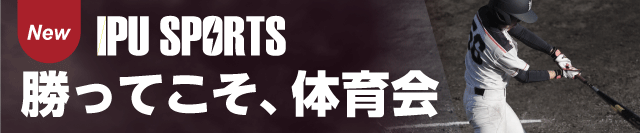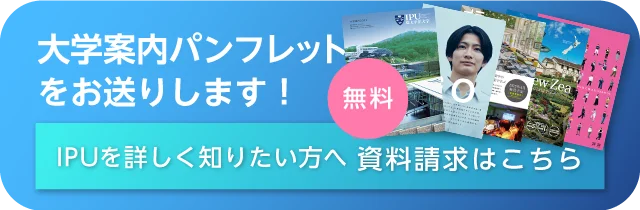なぜからはじめる保育原理
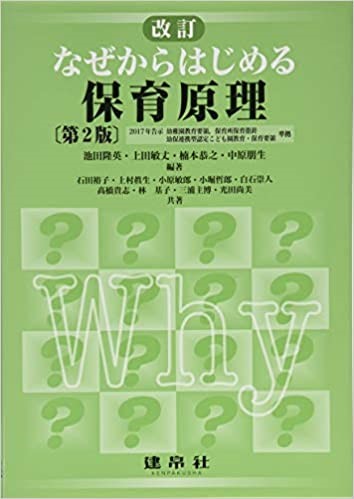
なぜからはじめる保育原理(改訂第2版)
著者名:池田隆英・上田敏丈・楠本恭之・中原朋生(編著)
出版社:建帛社
初版:2018年4月(改訂第2版)
ISBN:9784767950716
著書の内容
従来の保育原理のテキストで多く見られた「保育についてはこう考えるべきだ」との「べき論」の表現を避け,統計や文書などの資料を提示しながら「根拠をもった論述」を強く意識して展開する。
1章 保育の理念と概念―なぜ保育という言葉が生まれたのか?
2章 保育対象としての子ども―なぜ子どもを保育するのか?―
3章 福祉としての保育―なぜ保育所は必要なのか?―
4章 就学前教育・保育の基準―なぜ保育所保育指針が必要なのか?―
5章 発達過程に応じた保育―なぜ子どもの発達理解は大切なのか?―
6章 保育実践の構成原理―なぜ保育実践が成り立つのか?―
7章 保育のねらいと内容―なぜごっこ遊びをするのか?―
8章 遊びと環境構成―なぜ保育所には遊具があるのか?―
9章 保育実践のPDCAサイクル―なぜ保育者は記録をとるのか?―
10章 保育の思想史―なぜフレーベルは幼稚園を作ったのか?― 11章 日本の保育の制度史(戦前)―なぜ幼稚園には机と椅子があるのか?―
12章 日本の保育の制度史(戦後)―なぜ保育所と幼稚園があるのか?―
13章 保育における地域連携―なぜ保育所に地域の人が来るのか?―
第14章 保護者支援にける保育士の役割―なぜ保育士は保護者に声をかけるのか?―
15章 保育職務の全体像―なぜあなたは保育者になりたいのか?―補償 子ども・子育て支援新制度
著者コメント
本書は保育士養成の総論的な科目である「保育原理」を学ぶための入門書となっています。従来の書と異なり、データや資料をもとに、保育の見方考え方を探求的に学ぶことができます。
著書の内容
従来の保育原理のテキストで多く見られた「保育についてはこう考えるべきだ」との「べき論」の表現を避け,統計や文書などの資料を提示しながら「根拠をもった論述」を強く意識して展開する。
1章 保育の理念と概念―なぜ保育という言葉が生まれたのか?
2章 保育対象としての子ども―なぜ子どもを保育するのか?―
3章 福祉としての保育―なぜ保育所は必要なのか?―
4章 就学前教育・保育の基準―なぜ保育所保育指針が必要なのか?―
5章 発達過程に応じた保育―なぜ子どもの発達理解は大切なのか?―
6章 保育実践の構成原理―なぜ保育実践が成り立つのか?―
7章 保育のねらいと内容―なぜごっこ遊びをするのか?―
8章 遊びと環境構成―なぜ保育所には遊具があるのか?―
9章 保育実践のPDCAサイクル―なぜ保育者は記録をとるのか?―
10章 保育の思想史―なぜフレーベルは幼稚園を作ったのか?― 11章 日本の保育の制度史(戦前)―なぜ幼稚園には机と椅子があるのか?―
12章 日本の保育の制度史(戦後)―なぜ保育所と幼稚園があるのか?―
13章 保育における地域連携―なぜ保育所に地域の人が来るのか?―
第14章 保護者支援にける保育士の役割―なぜ保育士は保護者に声をかけるのか?―
15章 保育職務の全体像―なぜあなたは保育者になりたいのか?―補償 子ども・子育て支援新制度
著者コメント
本書は保育士養成の総論的な科目である「保育原理」を学ぶための入門書となっています。従来の書と異なり、データや資料をもとに、保育の見方考え方を探求的に学ぶことができます。
著者について
著者名:中原 朋生
役職:環太平洋大学次世代教育学部こども発達学科教授
専門領域:幼児期からの市民性育成・カリキュラム編成論
経歴:1970年山口県山口市に生まれる。1998年広島大学大学院教育学研究科博士課程前期修了。2013年博士(教育学)。2017年川崎医療福祉大学子ども医療福祉学科特任教授。2018年より現職。全国社会科教育学会理事。日本公民教育学会理事。